今日は「童謡の日」だそうです。
子どものころに何気なく口ずさんでいた歌にも、実は作り手の深い想いや、時代の背景が込められていることがあります。
今回は、そんな童謡の中から、『しゃぼんだま』と『雨ふり』という2つの歌に注目してみました。
優しい言葉の裏にある物語を、少しだけのぞいてみましょう。
私の好きな童謡の楽譜はこちら↓
|
|
1918年7月1日、児童文学雑誌『赤い鳥』が、鈴木三重吉によって創刊されました。
この日を記念して、「童謡の日」と呼ばれています。
子どもたちの感性を大切にした童謡の始まりを記念する日です。
「しゃぼんだま とんだ やねまで とんだ
やねまで とんで こわれて きえた」
初出は1922年、仏教児童雑誌『金の塔』(後の『金の星』)に詩が掲載されました。
翌1923年に中山晋平が曲をつけ、「童謡小曲」に収録されたことで広まりました。
童謡詩人・野口雨情によるこの詞は、一見、子どもが遊ぶ光景を描いているように見えます。
けれども、実は早くに亡くなった自分の娘を想って書かれたともいわれています。
「生まれてすぐに亡くなった赤ん坊を見て、命とはしゃぼんだまのようなものだと思った」
という、雨情の逸話も伝えられています。
ただし、これが歌詞の直接的な動機であったかどうかには諸説あり、仏教的な死生観とともに、後世に広く語られるようになったとも言われています。
軽やかなメロディの中に、人の命の儚さと愛しさが、そっと込められているように感じられます。
「あめあめ ふれふれ かあさんが
じゃのめでおむかえ うれしいな」
この歌が初めて発表されたのは、1925年、児童雑誌『コドモノクニ』の11月号でした。
「ピッチピッチ チャップチャップ ランランラン」と続く軽快なリズムと、蛇の目傘(和傘の一種)を差して母親が迎えに来る情景が、とても印象的な一曲です。
作詞は北原白秋、作曲は中山晋平。
雨の中をお母さんが迎えに来てくれるーーそんな、あたたかな場面が描かれています。
注目したいのは、当時としては「母親が子どもを迎えに行く」という描写自体が珍しかったということです。
当時の家庭像では、子育てを祖母や乳母が担うことも多く、母親が直接世話をする場面は、一般的ではなかった時代です。
その中で白秋は、あえて「母が子を迎えに行く」という情景を描きました。
そこには、家族の愛情や、子どもをやさしく見守るまなざしへの憧れや理想が込められているのかもしれません。
子どもの歌だと思っていた童謡も、目を凝らすと、作り手の深い思いが浮かび上がってきます。
童謡の日に、そんな優しさや祈りに触れてみるのも、素敵な時間かもしれませんね。
さて、あなたの心に残る童謡はなんですか?
![]()
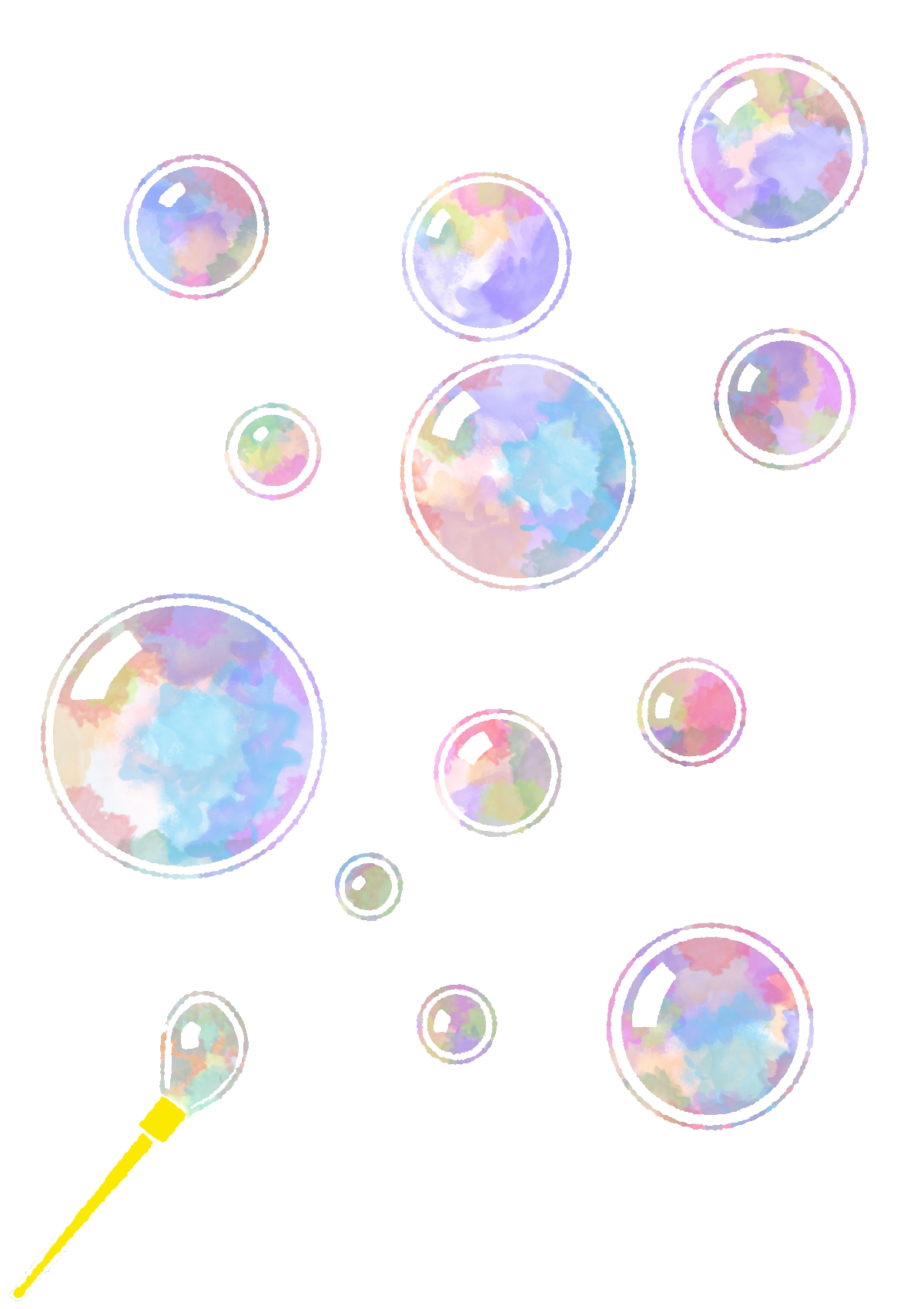
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47909be0.be4877da.47909be1.5eaa863b/?me_id=1213310&item_id=11151598&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2436%2F9784564602436.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)


コメント