9月になると、日が少しずつ短くなり、稲が色づき、赤とんぼが舞い、虫の音が響いてきます。
空気は澄み、朝晩の風は涼しく、夏の名残を感じつつも、確かに秋が始まっているなあと実感します。
そんなとき、自然と音楽の中にも「秋」を探したくなるのです。
メンデルスゾーン《Herbstlied(秋の歌)》Op.63-4
|
|
二重唱とピアノ伴奏による小品です。
私は以前歌ったことがあって、とても思い入れのある曲です。
詩はカール・クリンゲマンによるもので、「人生の喜びはすべて過ぎ去ってしまった」と嘆く内容。
秋の寂しさと深い孤独を映し出しています。
この曲は「6つの二重唱 Op.63」の一つで、メンデルスゾーン晩年の作品(1844年)。
彼は友人や家族との親しい音楽の場で、こうした二重唱をよく取り上げました。
ピアノ伴奏は和声的に繊細で、歌の切なさをさらに際立たせます。
声部同士のやりとりも美しく、秋の「すれ違う心」を象徴しているようにも聴こえます。
ドビュッシー《枯葉(Feuilles mortes)》― 前奏曲集第2巻 第2曲
|
|
ドビュッシーが1913年に完成させた「前奏曲集第2巻」の第2曲。
印象派の代表作のひとつで、静かに舞い落ちる葉を思わせる下降音型が特徴的です。
この曲では半音階的な和声進行や全音音階の響きが使われ、調性が曖昧に揺らぎます。
それによって、秋の「移ろい」「不安定さ」が聴覚的に表現されています。
冒頭の下降する旋律は落ち葉の舞い降りる動きを、和声の変化は光と影が交錯する秋の空気感を描いているようです。
外を歩いていて、ふと足元に落ち葉を見つけたときの感覚に近いものがあります。
立ち止まって、季節を味わいたくなる一曲です。
Kalafina《九月》(2011)
|
|
梶浦由記さんによる作詞・作曲。Kalafinaの多層的なハーモニーが秋の夜を幻想的に描きます。
歌詞では「秋の雫」「消えゆく九月」「見えない月」など、季節の終わりと恋の儚さが重ねられています。
クラシック音楽の世界では秋が「別れ」「移ろい」と結びつくことが多いですが、この楽曲もその系譜に連なると感じます。
梶浦由記さんは、クラシックの旋法を思わせるスケールの使い方や、声部の重なりを丁寧に扱い、透明感と神秘性を与えています。
音楽学的にも興味深い作品です。
童謡《小さい秋みつけた》(1955)
|
|
サトウハチロー作詞、中田喜直作曲。
日本の童謡の中でも「秋」を繊細に描いた名曲です。
「おへやは北向き くもりのガラス」というフレーズには、幼少期に病気療養をしていたサトウの記憶が投影されていると言われています。
外に出られない子どもが、耳で虫の声を聴き、窓越しに秋の気配を感じる――その内面の感受性が音楽となったのです。
中田喜直の音楽は、メロディの素直さと和声の繊細さが特徴。
童謡でありながら、和声の進行に微妙な陰影があり、大人になってから聴くと一層沁みます。
坂本真綾《月と走りながら》(2005)
|
|
アルバム『夕凪LOOP』に収録されたバラード。
作詞・作曲・編曲は浜崎貴司さん。
歌詞には「秋の月」「駅のホーム」「最終電車」などの情景がちりばめられ、都会的でありながら普遍的な「別れの秋」が描かれます。
坂本真綾さんの透明感ある歌声とシンプルな編曲が、言葉にできない想いをそっと包み込みます。
クラシック音楽でいうと、シューマンやブラームスの歌曲に漂う「夜と別れの情感」ともつながっているように感じます。
こうして振り返ると、私にとって9月は「静けさと切なさ」を音楽が代弁してくれる季節です。
感傷と季節の移ろいを、音楽を通してじっくり味わいたいですね。
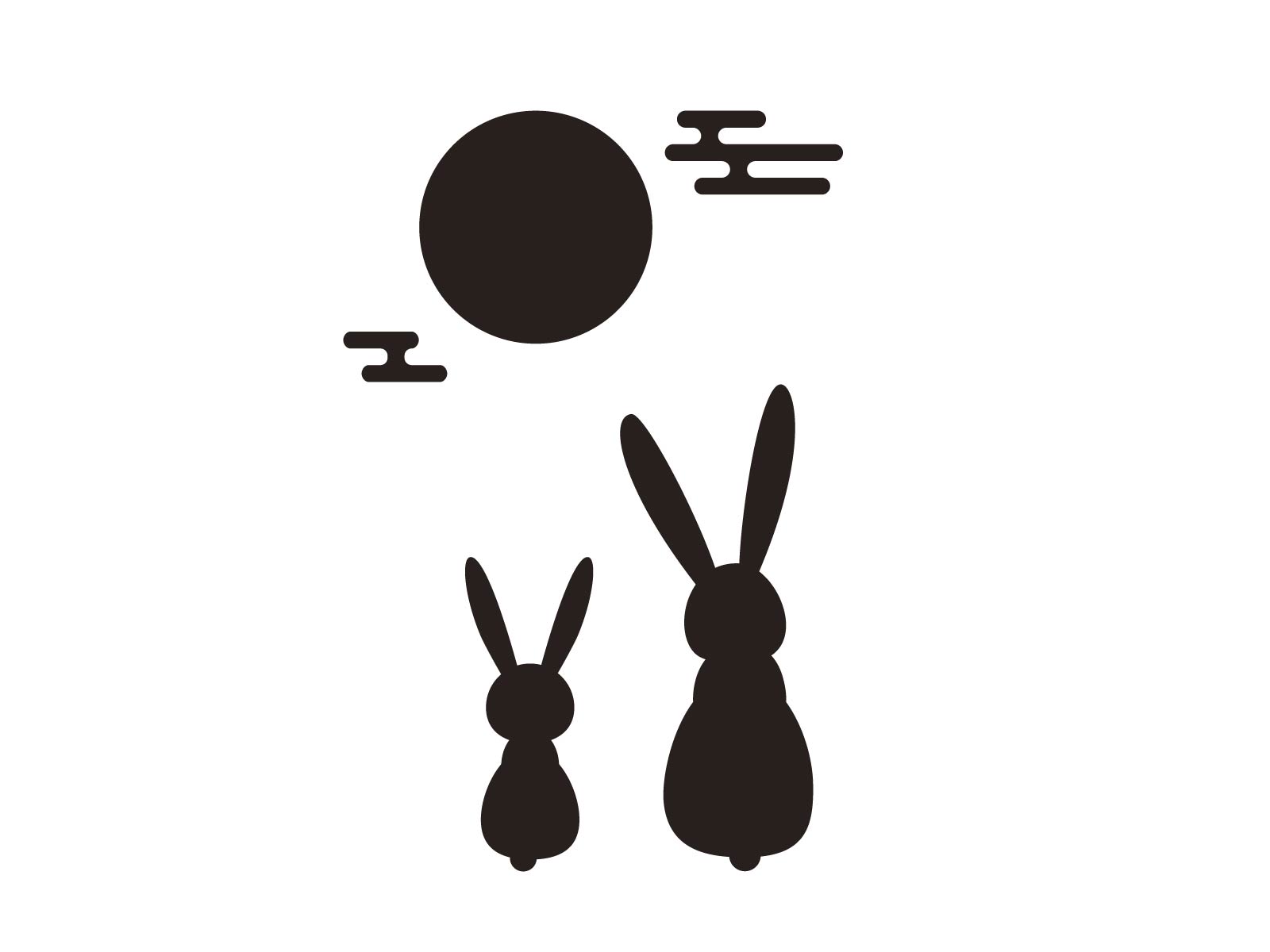







コメント